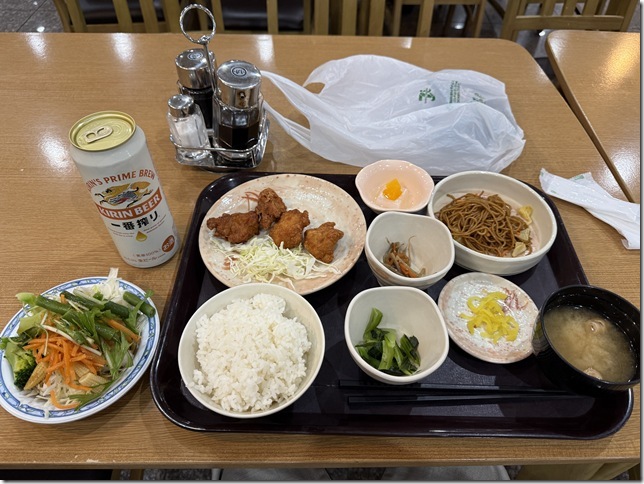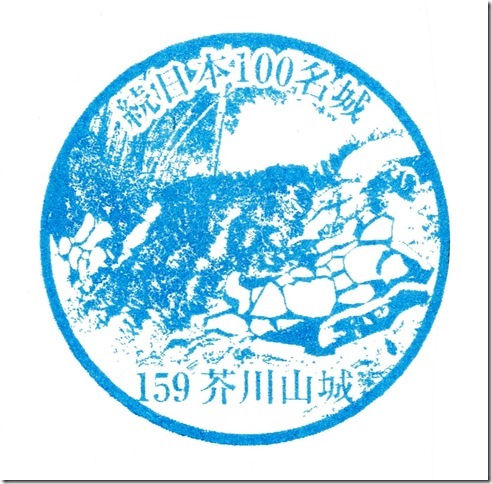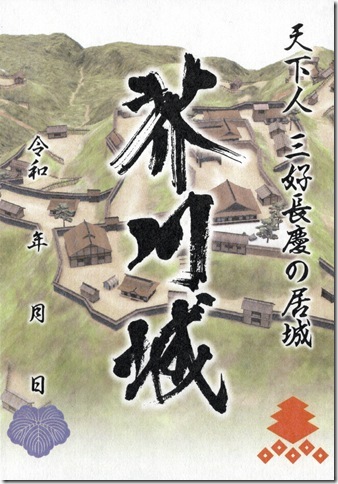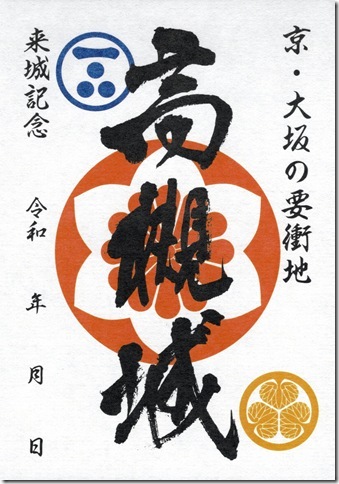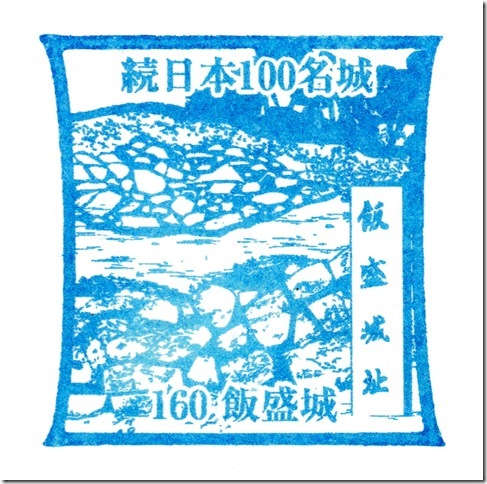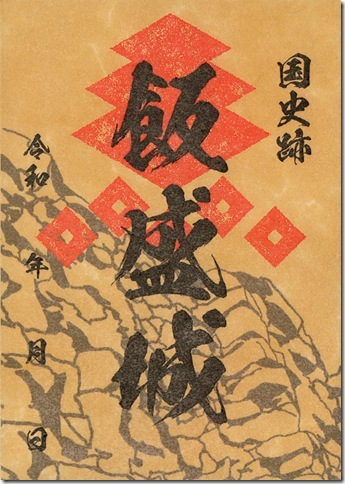部屋からのながめ
 ニューコマンダーホテル 大阪 <寝屋川>
ニューコマンダーホテル 大阪 <寝屋川>
3泊4日の大阪・兵庫めぐりの旅3日目。城めぐり再開、飯盛城、芥川山城を巡る予定です。どちらも山城で疲れそう。
6:40ごろホテルを出発しました。
■ 飯盛城 ■
飯盛城は大東市および四条畷市にまたがる飯盛山にある続日本100名城の160番、国指定史跡です。戦国時代に三好長慶が居城としたことで知られ、長慶は芥川山城からここに拠点を移しました。この城は政権が所在する「首都」といえるような場所で織田信長に先駆ける天下人ともいわれているそうです。
大東市側にある飯盛城跡駐車場に7:20ごろ到着しました。スタンプと御城印があるキャンピィだいとうは10時からなので、先に登城します。

飯盛城跡駐車場

飯盛城跡案内図
駐車場のある道が登城道、そのまま上っていくと途中2本連続して竪堀を見ることができます。


竪堀
さらに進むと馬場(X郭)で楠公寺があります。トイレの壁面にパンフレットがあるはずが、空っぽでした。楠公寺は楠木正行はじめ四條畷の戦いの戦死者を弔うために開山されたお寺で、高櫓郭には小楠公銅像があります。

馬場(X郭)
楠公寺に向かって左には登城道が続き、しばらく登ると三方向への分岐に出ますが、右の山道を進み少し行くと石垣1があります。崩壊防止のための布団かごが設置されていました。この山道の下側にも石垣69があるはずなので少し探しました。あれかなぁと思われる石垣を木の枝の間から見つけましたが正しいかどうか。



石垣1

石垣69
山道を戻り、先ほどの分岐を道なりに登っていくと高櫓郭(Ⅰ郭)と千畳敷郭(Ⅷ郭)の間の大きな堀切に出ます。


堀切
ここを境に大きく北側と南側に分かれていて、先に北側を見ていきます。2本の階段がありますが、どちらも高櫓郭(Ⅰ郭)に行けるようです。堀切と土橋があり、ここを登ると高櫓郭(Ⅰ郭)ですが手前はロープのある急な登り坂でした。


堀切と土橋

急な登り坂
高櫓郭(Ⅰ郭)に出ました。高櫓郭(Ⅰ郭)は飯盛山の山頂です。高櫓郭(Ⅰ郭)には、小楠公銅像(楠木正行像)があり、その横には戦時中に供出された小楠公銅像を再建した田伐兼松の像、他に国旗掲揚台があります。

小楠公銅像(楠木正行像)

田伐兼松銅像

国旗掲揚台
高櫓郭(Ⅰ郭)から北側すこし下がったところが本郭(Ⅱ郭)で、展望台からは大阪平野が一望できます。

展望台

展望台からの眺望

展望台からの眺望(大阪城)
本郭(Ⅱ郭)から北側すこし下がったところがⅢ郭で、Ⅲ郭手前右方向の山道を行ってみると、石垣3・石垣4を見ることができます。


石垣3

石垣4
Ⅲ郭から西側にある曲輪群A・北條神社へ続く山道を少し下りると石垣5・6・7があります。


Ⅲ郭

石垣5

石垣6(上)・7(下)
Ⅲ郭から北側への山道はかなり急になっています。下りたところは旧道と新道へ分岐になっていますが、旧道は法面崩壊の恐れがあるため新道へとの案内が出ていました。三本松丸(Ⅳ郭)はここをすこし上がった旧道沿いのため、安全そうなところまで行って戻ってきました。

Ⅲ郭北側山道

旧道新道分岐

三本松丸(Ⅳ郭)
新道へ進みます。分岐を下りだしてすぐ右に振り替えると山道の下側に石垣90が確認できました。


石垣90
進むと御体塚郭(Ⅴ郭)の南側に出ますが、その手前右側には石垣14・15・16が確認できます。

石垣14・16

石垣14

石垣16

石垣15
階段をずっと登ると御体塚郭(Ⅴ郭)です。御体塚郭(Ⅴ郭)は三好長慶の死を公表しなかった2年間の仮埋葬地だといわれています。


御体塚郭(Ⅴ郭)
Ⅵ郭へ向かいます。御体塚郭(Ⅴ郭)北側から山道を下りていくと右側に石垣18がありました。さらに下りて、御体塚郭(Ⅴ郭)とⅥ郭間の大堀切にでました。岩盤が削り抜かれいていて見事です。

大堀切
大堀切を左手に山道を進むと北端のⅥ郭です。比叡山、六甲山、淡路島、南河内まで見渡せる視界270度の眺望が広がります。





Ⅵ郭

飯盛山史蹟碑
ここまででⅠ郭からⅥ郭までの北側遺構を見たので、Ⅴ郭(御体塚郭)の東側の山道経由で南側へ戻ります。途中で石垣19を確認できました。

石垣19
御体塚郭(Ⅴ郭)の南側でもと来た山道に合流し、三本松丸(Ⅳ郭)南側の分岐(行きに通った旧道新道分岐)で左側石垣1方向へつながる山道を進みます。Ⅲ郭東側あたりでⅢ郭へつながる山道に進みすこし上がったところに石垣9、つづいて石垣54を確認しました。

Ⅲ郭へつながる山道(右)

石垣9

石垣54
Ⅲ郭に戻り、石垣3・4を経由してそのまま進んでいけば石垣71が見られるはずでしたが、よくわかりませんでした。
そのまま進んで、高櫓郭(Ⅰ郭)と千畳敷郭(Ⅷ郭)の間の大きな堀切へ戻ってきました。これから南側を見ていきます。管理用道路を登るとっていくと千畳敷郭(Ⅷ郭)です。千畳敷郭の最高部にはNHK・FM送信所が立っています。
中断を西方向へ行くと土塁が見られます。


千畳敷郭(Ⅷ郭)

土塁
千畳敷郭(Ⅷ郭)の南側は南丸(Ⅸ郭)です。南丸(Ⅸ郭)には石垣で築かれた虎口があります。



南丸(Ⅸ郭)

石垣31(左)石垣30(右)と虎口

石垣30
これで飯盛城散策は終了、行きとは違う道で帰りました。虎口から南へ道なりに進み、途中、「桜池・野外活動センター」の道標で左折し、山道をひたすら下っていくと駐車場近くまで戻れました。

「桜池・野外活動センター」の道標
時刻はちょうどキャンピィだいとうが開館するちょうど10時すぎ、スタンプと御城印をゲットしました。
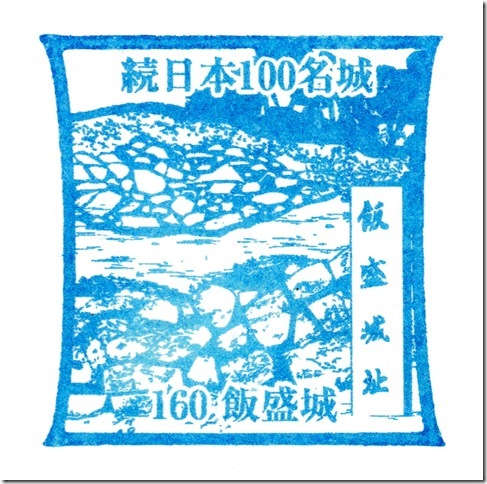
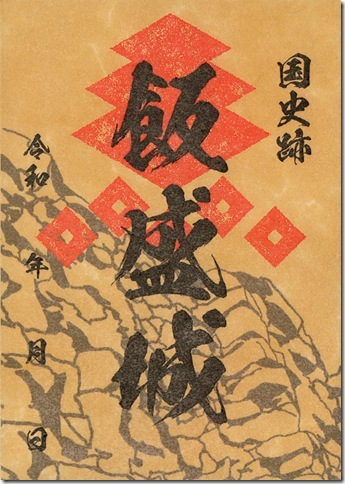
次は芥川山城へ向かいます。